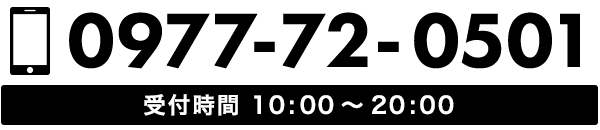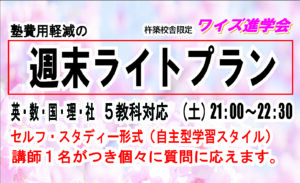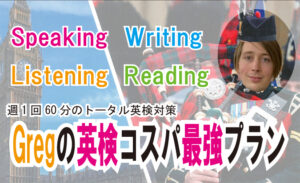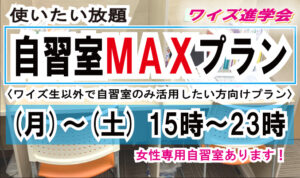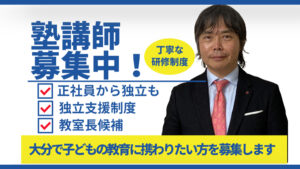社会一文字シリーズ
11月になりまして、最近急に寒さを感じるようになってきました。
秋が仕事していないですね。秋はもっと自己主張して欲しいです。
担当Kは四季の中では一番秋が好きです。過ごしやすいので…。
皆さん、体調管理はしっかりと、インフルエンザやコロナも流行っているのでご注意を!!
さて、今回のテーマは社会一文字シリーズ!!
ついこの間のことですが、社会が苦手な生徒から
「租とか座とか隋とか何なん?」
との質問をいただきました。漢字一文字の用語が同じに見えるそうです…。
確かに公民の○○法みたいに、名前から得られる情報が少ないので、ごちゃごちゃになりそうですね。
今回はここからいくつかお話を、、、
まず、「隋」とは中国の王朝の名前ですね。
日本は島国なのでこの辺りの感覚は薄いですが、大陸の国は周辺諸国との戦いの歴史が多いです。
中国を始めとしてヨーロッパとかもですね。
新しい国ができて、滅ぼされて、また新しい国ができ、名前が移り変わっていきます。
殷・周・秦・漢・隋・唐・宋・元・明・清
これらは中国の王朝の名前です。当然この間にも他に国があるのですが、中学生の教科書範囲はこの辺りですね。
秦は「キングダム」、漢は「三国志」の話ですね。
担当Kはこの辺りの時代のものが好きで、よく読んでいます。
次に、
「租」ですが、これは 「租・庸・調」のセットで、奈良時代の税制度ですね。
班田収授法により、6歳以上に口分田が配られます。
口分田が割り当てられると、納税の義務が発生します。
租はお米
庸は布
調は特産物 を納めます。
とくに庸と調は都に直接納めに行かないといけないので、農民の負担が大きかったです。
さて、最後は
「座」ですね。これは中世の商業の組合です。
同じ業種の商人が手を組んで、営業を独占します。
領主は座を認める見返りに、営業税を取ります。
これにより、商人の利益は上がりますが、その分価格が上がるので、農民にはいろいろと厳しいものでした。また、新規の商人は営業の妨害を受けました。
織田信長は楽市楽座の政策でこの座を廃止し、自由な商工業が行われるようにしました。
その結果。信長の城下町は経済発展を遂げ、天下統一事業の後押しになりました。
ちなみに、座と同じような組織に株仲間がありますが、こちらは江戸時代の同業者組合ですね。
また、中世には同じ一文字の用語で、「惣」がありますね。
こちらは農民の自治組織のことですね。
さあ、このように一文字の用語にもそれぞれの意味があります。
社会は知識が多くて大変ですが、この辺りきちんと区別していきましょう。
こういうテーマでまとめてみても面白いですね。
担当K
担当KはワイズX(旧:twitter)(https://twitter.com/wiseshingakukai)も担当しています。
日々ツイートのネタ探しをしていますので、よかったら覗いてみてください。