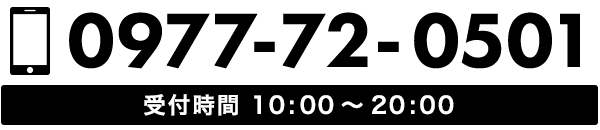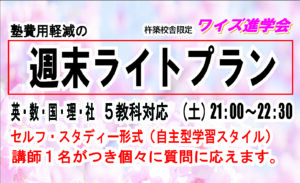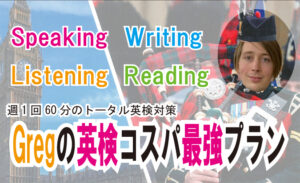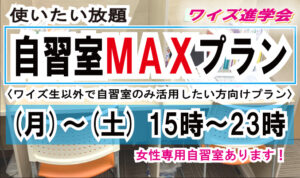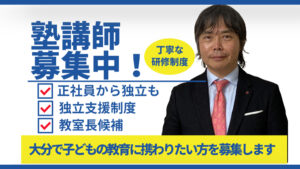高校入試の社会科の話
梅雨が明けて暑くなり、気付いたらもう7月ですね。
2025年も既に半年が過ぎました。
年々月日が経つのが早くなっている気がしますね。
新しい経験が少ないと、時間は早く感じてしまうらしいので、いつまでも新しいことに挑戦して、新鮮な気持ちでいたいですね。
さて、今日は高校入試の社会の話です!!
過去に社会科の勉強法について記事をあげたことがありますが、年々アップデートされていきます、それにあわせて対策もどんどんアップデートしていきましょう!!
新しいものを取り入れて、自分をアップデートしていくことが成長への鍵です。
なぜこの時期に入試の話なのか?
それは志望校決定に直結する大事な模試「学力診断模試」が9/2と10/30に控えているからです。意外ともう時間は残されていないかもしれませんよ。
まずは昨年度の高校入試のおさらいから、
平均点が 143.2 点でここ数年で最低ラインです。
とくに社会科は平均 27.2 点、 一昨年が 32.3 点だったのに対しかなり下がっています。
また、最高点が56点と、他の科目に比べて満点もいませんでした。
点数ごとに比べてみると、
40点以上は上位15%のみ、20点代が31.1%で一番のボリュームゾーンと低めの水準になっています。
中学生の教科書は今年新しいものに変わりました、5年ごとに改訂されるたびに、新しく加わったもの、逆に削減されたもの、多少はありますが、必要とされる知識はそうそう大きく変わっていません。
では、なぜ平均点が下がったのか? 難易度が上がったのか?
実際のところ問題の解答数はそんなに変わっていません。ただ、単純暗記では点にならなくなりました。大きな変化は、
①用語を聞く問題の減少
②解答を導くまでの過程の増加 この2点です。
社会科はどうしても必要とされる知識、要は覚えることが多い科目ですので、
知識量=点数につながる という形が長年ありました。
それが、単純暗記で点が取れるという認識になったのではないでしょうか。
最近の入試は出題側の「きちんとした知識・理解に基づいた考えをして欲しい」という意図が見える気がします。
さて、上記2点を詳しく見ていきましょう。
まずは、①用語を聞く問題の減少
いわゆる、一問一答形式の問題の減少ですね。さらに、重箱の隅をつつくような解答ですね。
今年の問題であれば、「Iターン」や「征韓論」、一昨年まえの問題であれば「合理的配慮」といったところです。
これらの言葉は教科書には当然書かれています。しかし、多くの人が受験勉強に使ってるであろう新研究には載っていないものもあります。新研究はよくまとめられているいい教材ですが、あくまで補助教材です。
受験のメインは教科所です!!
社会が苦手な人は、教科書を開いたことないなって人も多いのではないでしょうか。
教科書には当然用語だけでなく、それらの説明・補足事項も載っています。きちんとそれらを踏まえたうえで正しい知識を身に付けてください。
次は、②解答を導くまでの過程の増加
例えば、正誤問題について、
これまでの出題形式であれば、
ア 桶狭間の戦いで今川義元を破った。
イ 本能寺の変で家臣の明智光秀に背かれた。
ウ 楽市・楽座で商工業の発展を促した。
エ 関ヶ原の戦いで、鉄砲を用い武田氏を破った。
さて、この織田信長がやったことで誤っているものはどれでしょう。
当然答えは エ ですね。
武田氏を破った戦いは「長篠の戦い」です。
これがこれまでの出題形式です。選択肢は文章ですが、それぞれ用語が入っていますので、そこで判断できます。
そして、今の出題形式ですが、
ア 駿河(現静岡県)の戦国大名を破り勢力を広げた。
イ 敵対する仏教勢力を武力で従わせた。
ウ 関所を設け通行税で商工業の発展を促した。
エ 鉄砲を有効に使用し、今川義元を破った。 この中で誤っているものの組み合わせを以下から、選びなさい。
1.ア・イ 2.イ・ウ 3.ウ・エ 4.ア・エ
こうした形式に変っています。一目見て、これだ!というわけでなく、選択肢を一つずつ吟味していく必要がありますね。
ちなみに正解は 3 ですね。
さあ、なぜそうなるかは教科書を見ながら考えてみてください!!
これら二つの問題を比べてみても、一問を解くまでの過程が長くなっていることが分かります。正しい知識、歴史であれば正しい流れを深く理解する必要がありますね。
あとは細かいところになりますが、記述の内容にも注意です。
例えばを挙げるなら、
生産量と輸出量 これらの値は必ずしも=ではありません。
人口が多い国では生産量が多くても自国での消費量が多いので、輸出量は多くありません。
また、資料を使った問題では、数値と割合にも注意です。
さて、長くなってしまいましたので、ここらで締めになりますが、
あたりまえですが、問題文をちゃんと読んでください。
資料の出典や年代など隅々までです!
そして、どんな問題かをしっかり理解したうえで対策を立てていきましょう。
勝つためにはまず敵を知るところからはじめましょう!!
担当K
担当KはワイズX(旧:twitter)(https://twitter.com/wiseshingakukai)も担当しています。
日々ツイートのネタ探しをしていますので、よかったら覗いてみてください。